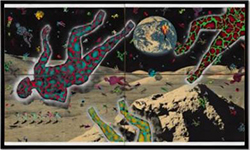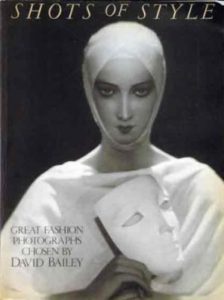2017年の1~3月にかけて、東京の3会場で開催し好評だった“BOWIE:FACES”展。いよいよ今週から名古屋に巡回する。会場はJR名古屋駅からも近い納屋橋 高山額縁店。会期は9月8日(土)~16日(日)まで。
本展では、テリー・オニール、ブライアン・ダフィー、鋤田正義など7名の有名写真家による、1967年~2002年までに制作されたデヴィッド・ボウイの珠玉のポートレート、写真家とのコラボレート作品約30点を紹介する。ボウイによる9枚のアルバムのオリジナル写真、および関連するアート作品が含まれる。
参加写真家は、ブライアン・ダフィー(Brian Duffy)、テリー・オニール(Terry O’Neill)、鋤田正義(Masayoshi Sukita)、ジュスタン・デ・ヴィルヌーヴ(Justin de Villeneuve)、ギスバート・ハイネコート(Gijsbert Hanekroot)、マーカス・クリンコ (Markus Klinko)、ジェラルド・ファーンリー (Gerald Fearnley)。なお彼ら全員が、昨年春に東京展が行われたヴィクトリア&アルバート美術館企画の”DAVID BOWIE is”に協力している。
実は、”BOWIE:FACES”展の巡回先探しには非常に苦労した。本展は、2016年に亡くなったデヴィッド・ボウイとセッションを行った複数の有名写真家の珠玉のオリジナル・プリントを展示。“アラジンセイン”、“ダイヤモンド・ドック”、“ヒーロース”などの当時のLPジャケットを飾った写真のオリジナル作品が含まれる。超一流の展示コンテンツだといえよう。
ただしプロジェクトのビジネス・モデルが東京以外の地域ではなかなか理解されなかった。つまり、本展は日本の一般的な、入場料収入を主な売り上げとするものではない。入場は無料で、スポンサーの協賛金、展示作品、カタログ等の販売で経費を賄い、利益を目指すもののだ。
東京ではブリッツとテリー・オニールのエージェントである英国のアイコニック・イメージスが中心になって、主催の実行委員会を立ち上げた。会場費、輸送費(海外/国内)、フレーム、ブックマット、会場設営、カタログ製作費、広報活動、スタッフなどの経費はすべて主催者が負担しないといけない。またスポンサー探しも独自に行うことになる。ブリッツは写真作品販売の経験が豊富なのでプロジェクト全体のリスクとビジネスの可能性はすぐに把握できた。
またアイコニック・イメージスは国内の外資系中心にスポンサー探しに尽力してくれた。協賛企業にとってはボウイのヴィジュアルを使用してブランド力の向上が図れる。外資系はこの点をよく理解して協力してくれた。
私どもの決断を後押ししてくれたのが、過去に行ったテリー・オニール展の経験だ。アート・ファン以外に、写真作品の価値が判断できる非常にリテラシーが高いロック音楽ファンが顧客として存在することが確認できたのだ。お陰様で、2017年1月~4月までに3会場で開催した東京展は、予想以上のコストがかかった割に赤字を出さずに終わることができた。
しかし東京以外の地域では、自らが主催者となって写真展を実行する会場がなかなか見つからなかった。ほとんどの企画スペースは、交渉してみると実際は場所貸のレンタル・スぺースだった。日本では写真は売れないとよく言われるが、東京以外では、状況はさらに厳しいのだと思う。
名古屋巡回展が実現できたのは、ブリッツと長く付き合いがあるコピー・ライターの岡田新吾氏の協力があったからだ。実は、彼は筋金入りのアート写真コレクター。以前、好きが高じて自らのアート写真ギャラリーを名古屋市で運営していたこともあるくらいだ。もちろん、昨年の“BOWIE:FACES”東京展も見に来てくれた。この企画を持ち込んだら、すぐに名古屋の実行委員会立ち上げに動いてくれた。岡田氏の今までの経験から、これはいけると判断してくれたのだろう。彼は優秀なプロデューサーでもある。瞬く間にアートやビジネス関連のネットワークを駆使して、展示会場を提供してくれる納屋橋 高山額縁店、アートへの協賛に理解を持つ、株式会社マグネティックフィールド、諸戸の家株式会社を見つけてきてくれた。彼の実行力にはいつも驚かされる。
“BOWIE:FACES”名古屋展は、岡田氏をはじめ実行委員会のメンバーの尽力と、協賛企業の援助により開催決定までたどりつけた。心より感謝したい。
さて会場では幅広い価格帯のオリジナル・プリントを展示販売する。中心価格帯は、10~30万円。しかしお買い求めやすい作品も数多くある。憧れの鋤田正義作品も、一部の小さいサイズの作品だと、額・マット込みで約3万円から、ブライアン・ダフィーのあの有名作“アラジン・セイン”も、LPジャケットのサイズのマット付きエステート・プリントならで約2万円で購入可能。
週末には私も現地で接客に当たる予定だ。見かけたら気軽に声をかけてほしい。
また、デヴィッド・ボウイの“Heroes”のジャケット写真で知られる鋤田正義氏を招いてスペシャルトークを開催する。鋤田氏の名古屋でのトークは今回が初めてとのことだ。ボウイを含む、鋤田正義氏の数々の作品画像やミニ・ドキュメンタリー動画をプロジェクターにて紹介。鋤田正義の写真家キャリアの変遷と将来の計画、デヴィッド・ボウイ撮影にまつわるエピソード、撮影と作品制作の流儀、国内外での最近の活動などについて語ってもらう予定。ただし、鋤田氏による会場でのサインは行わない。ご本人が高齢であることと、会場の混乱を避けるためなのでどうかご理解いただきたい。
ただし鋤田氏がカヴァーにサインを入れたカタログを限定数だけ販売する。こちらは希望者が多い場合は抽選販売となる。
“BOWIE:FACES”展は、東京、名古屋に続く巡回先をまだ募集中だ。興味ある人はぜひ問い合わせてほしい。
・鋤田正義スペシャルトーク概要
日 時:9月8日(土)14:00~15:30(開場13:30)
会 場:電気文化会館イベントホール
定 員:200名 ※お申込み方法は オフィシャルサイトをご覧ください。
http://bowiefaces.com/
参加費:2,500円
・写真展の概要
開催時期:
2018年9月8日(土)-16日(日)9:00-19:00
(日曜/12:00-19:00)
最終日は18:00より撤収作業を開始します。お早めに来場ください!
開催場所: 納屋橋 髙山額縁店2F
名古屋市中村区名駅南一丁目1-17
http://nayabashi-gakubuchi.jp/publics/index/7/