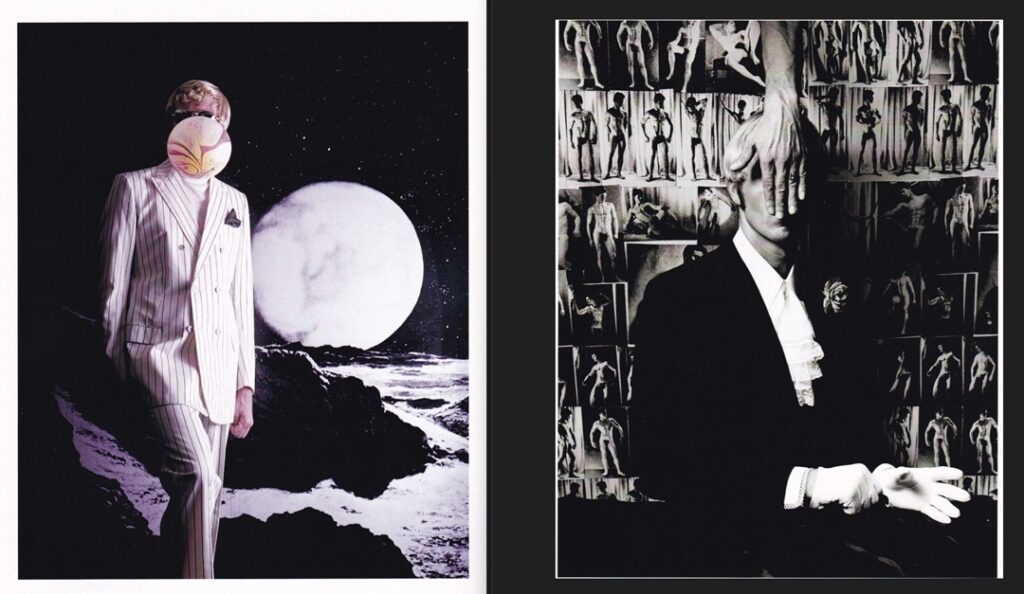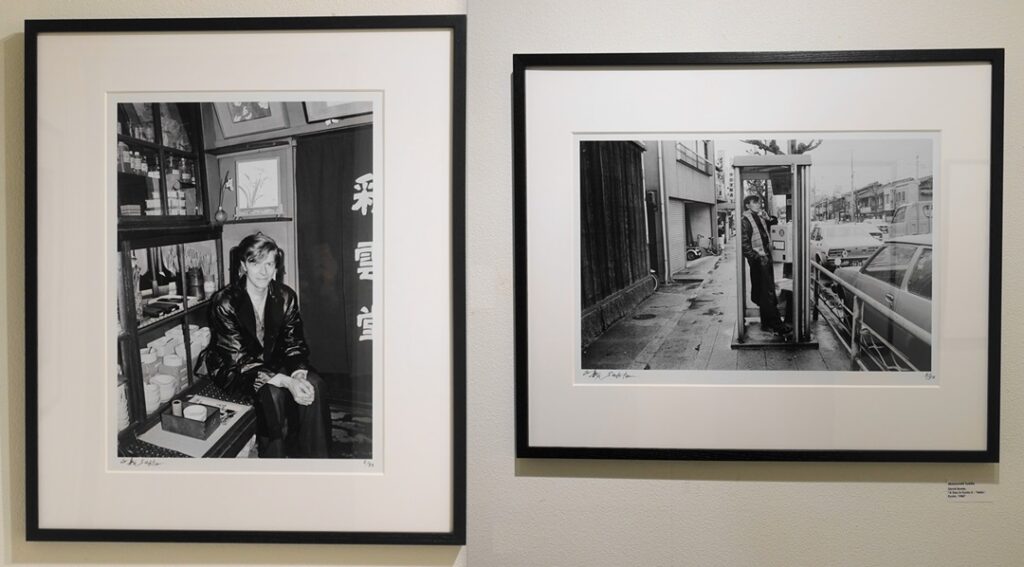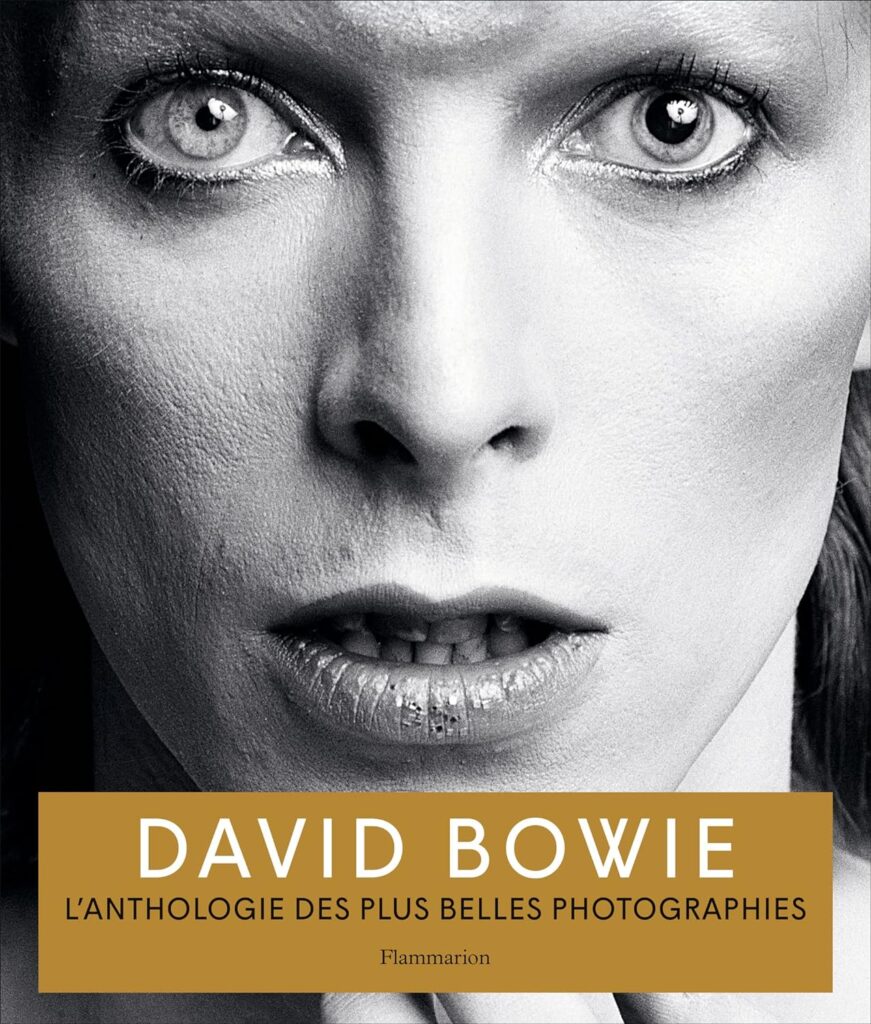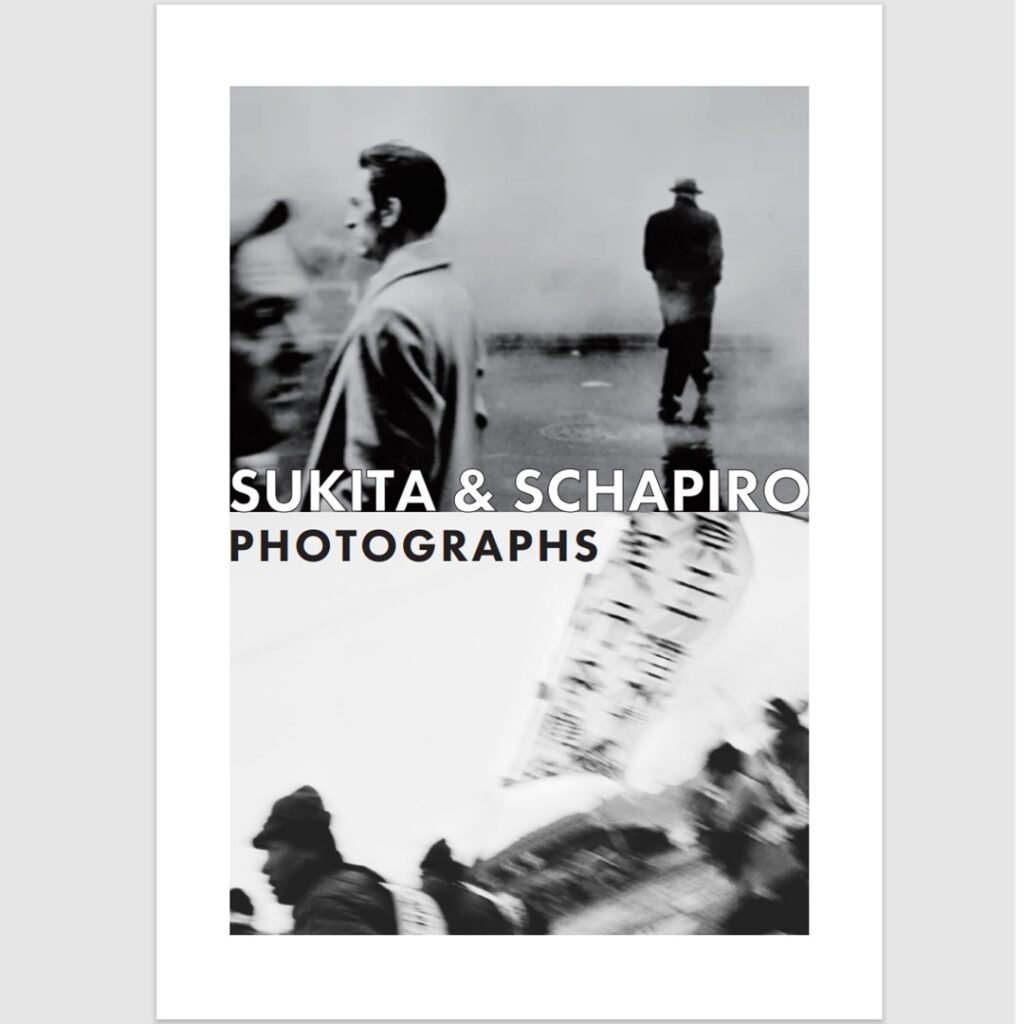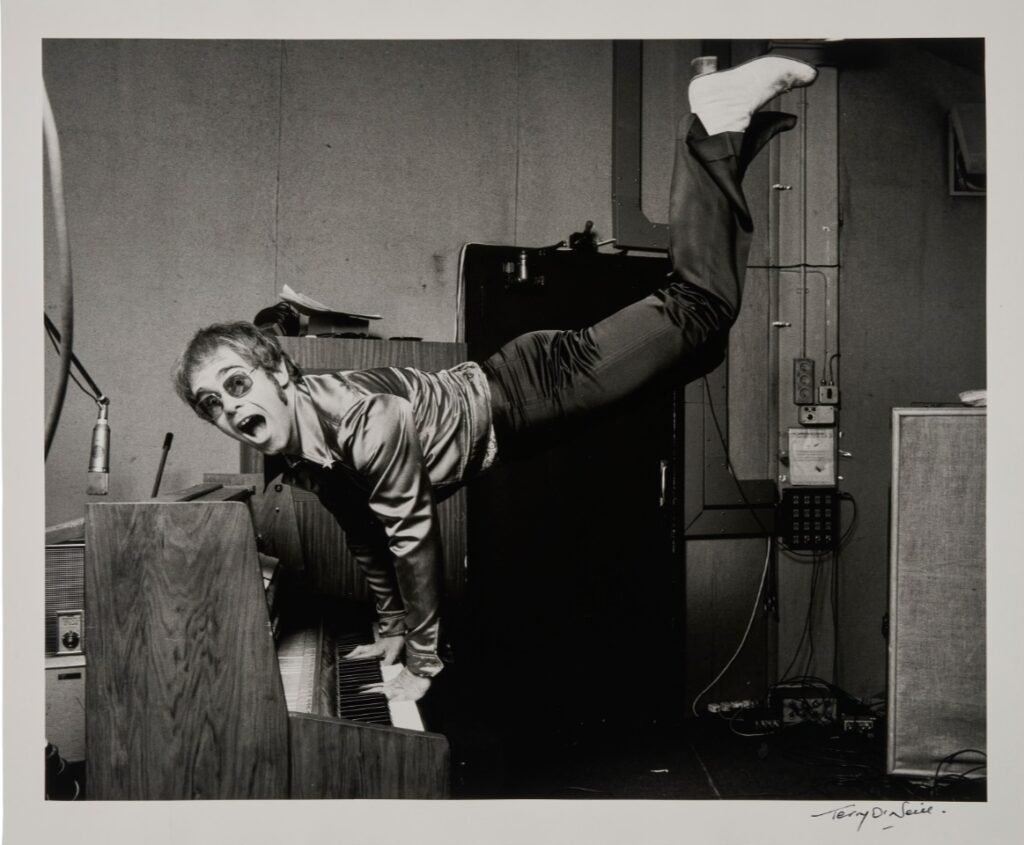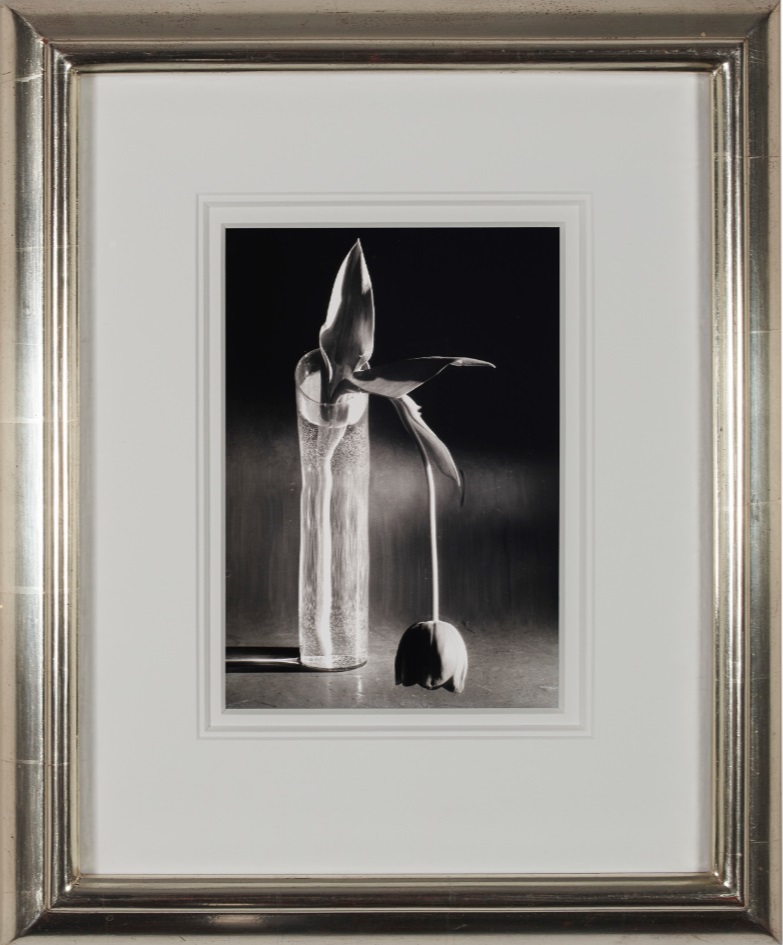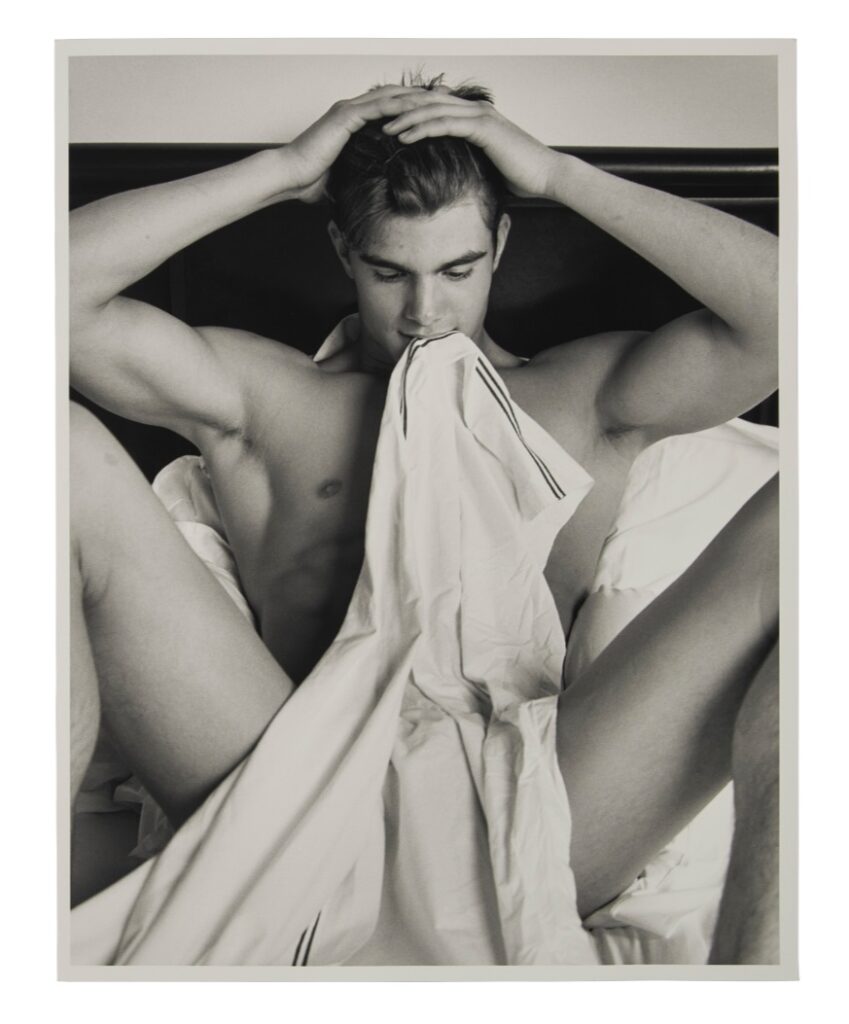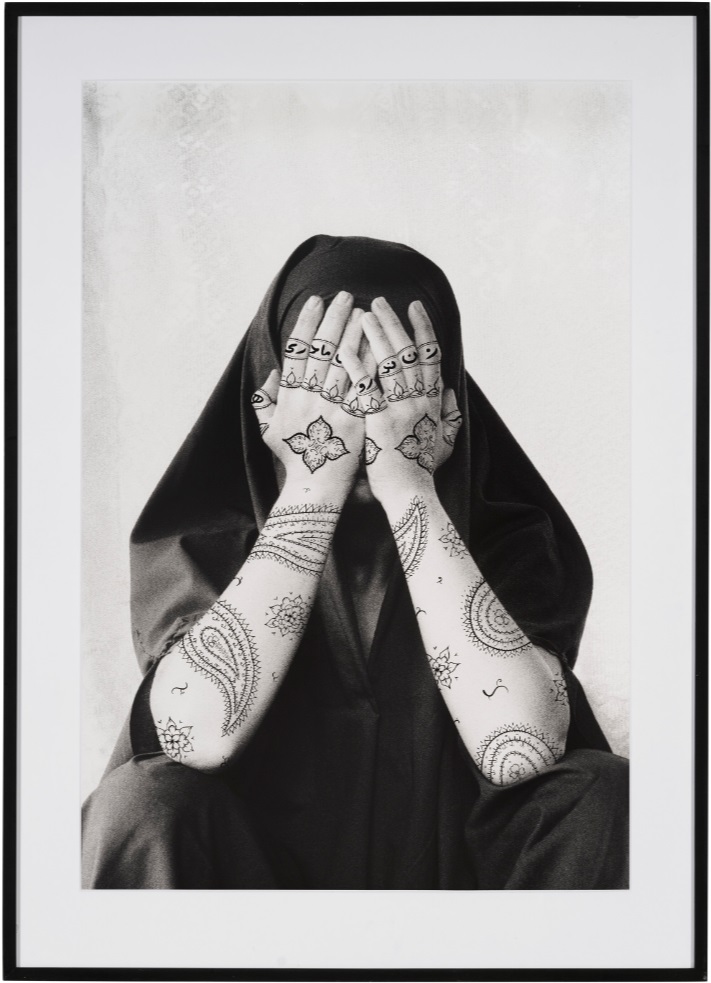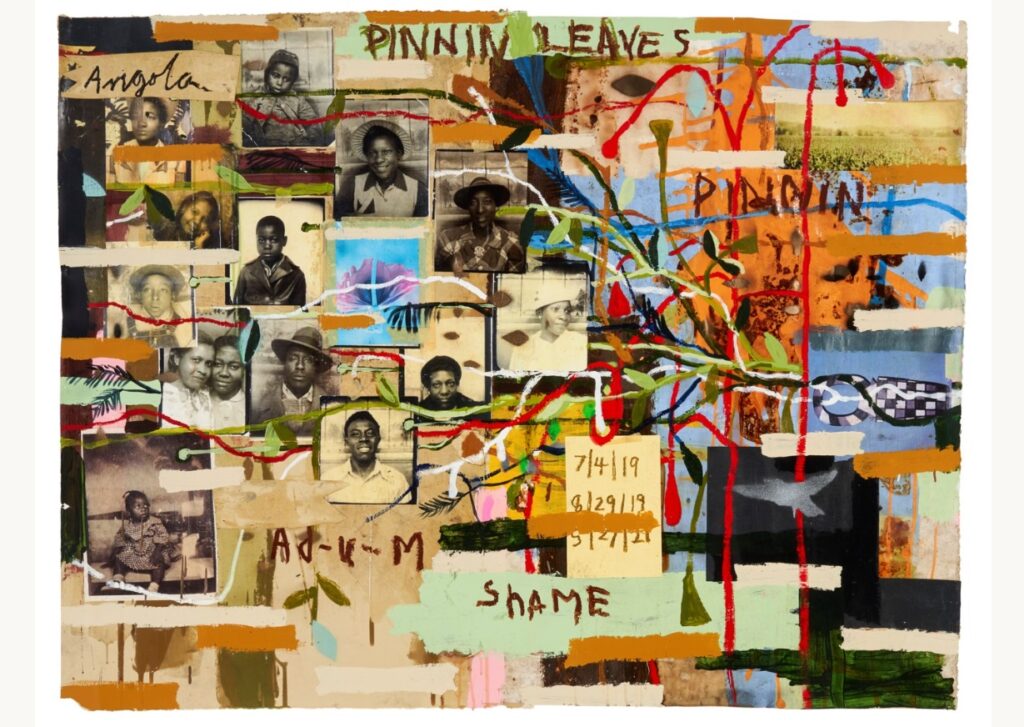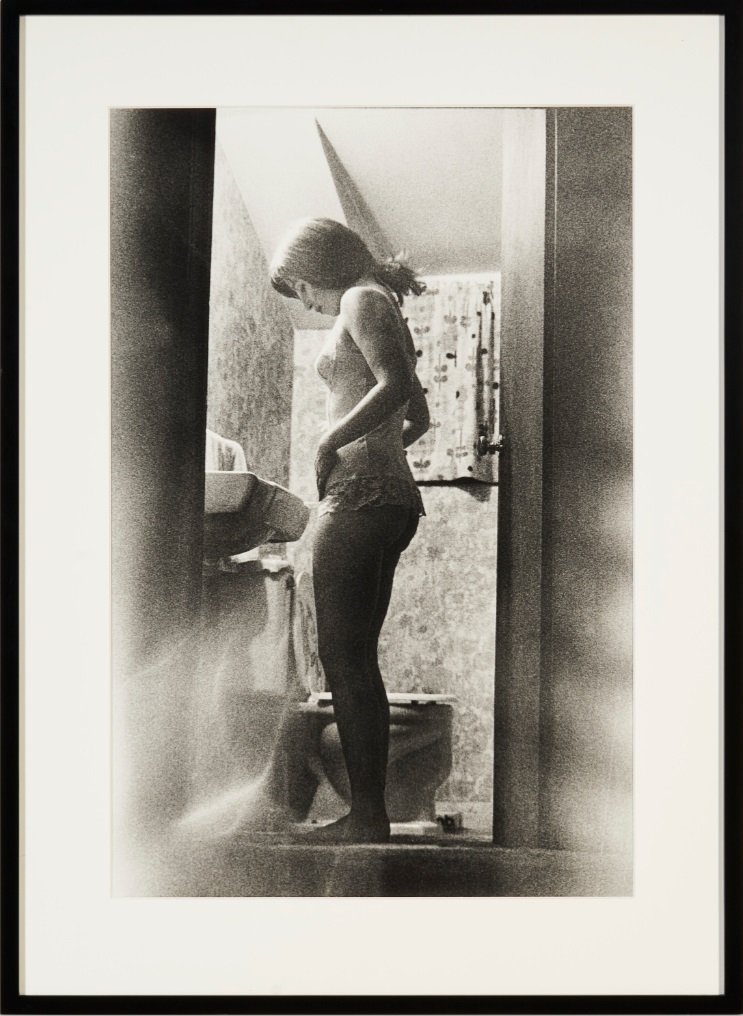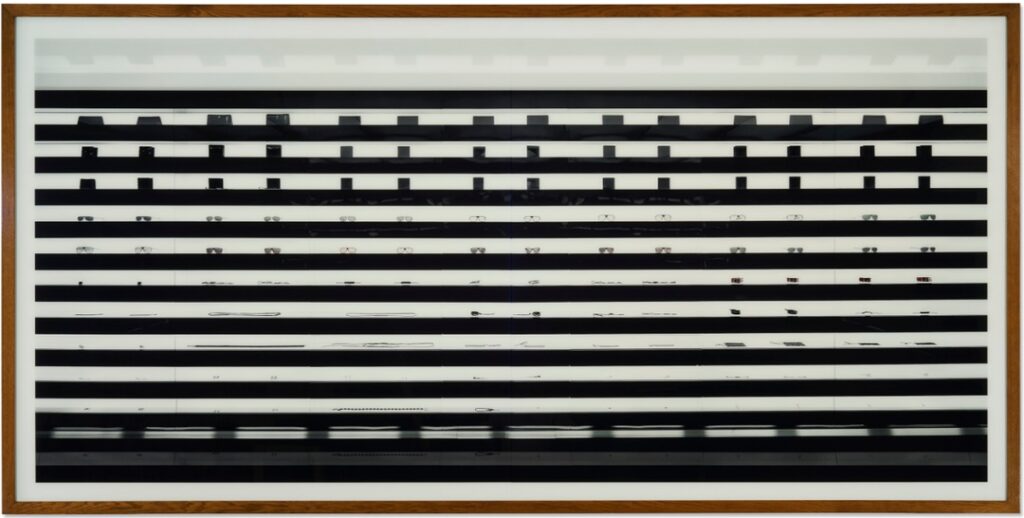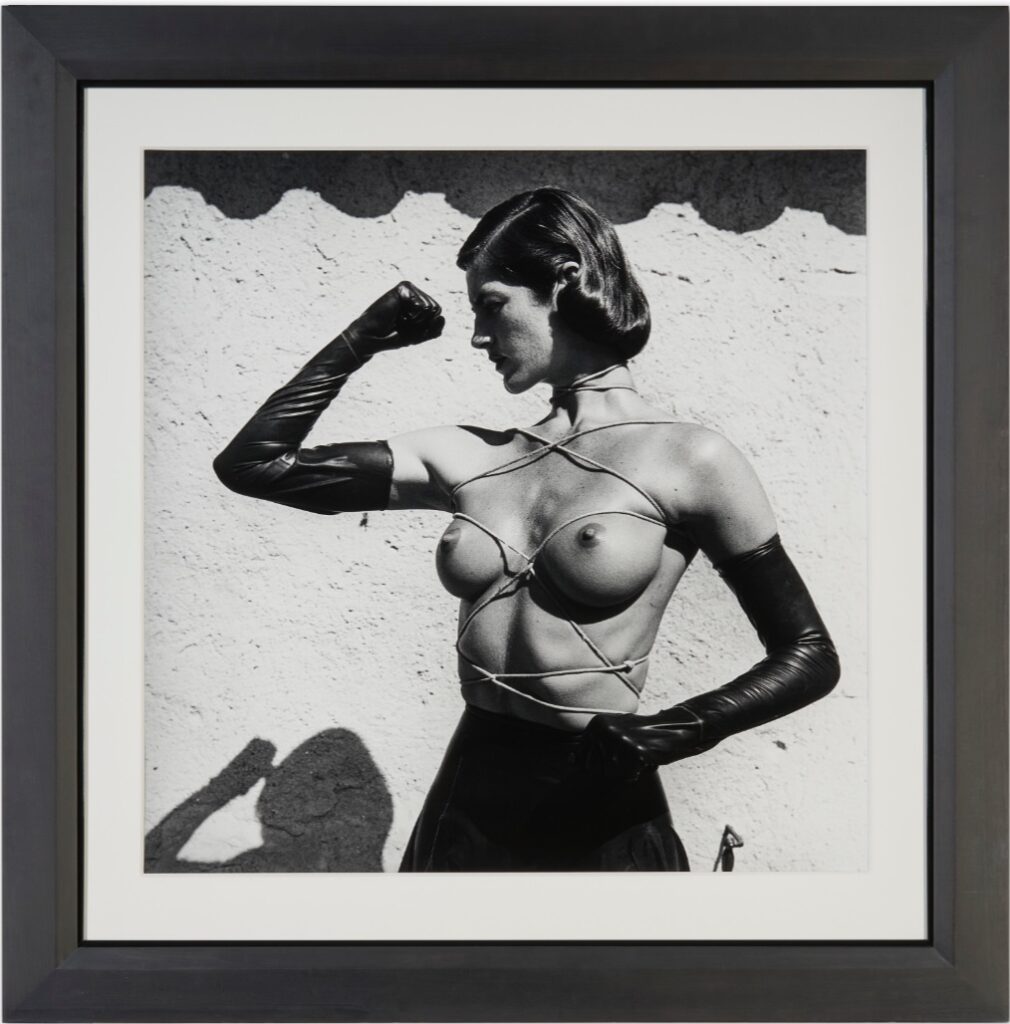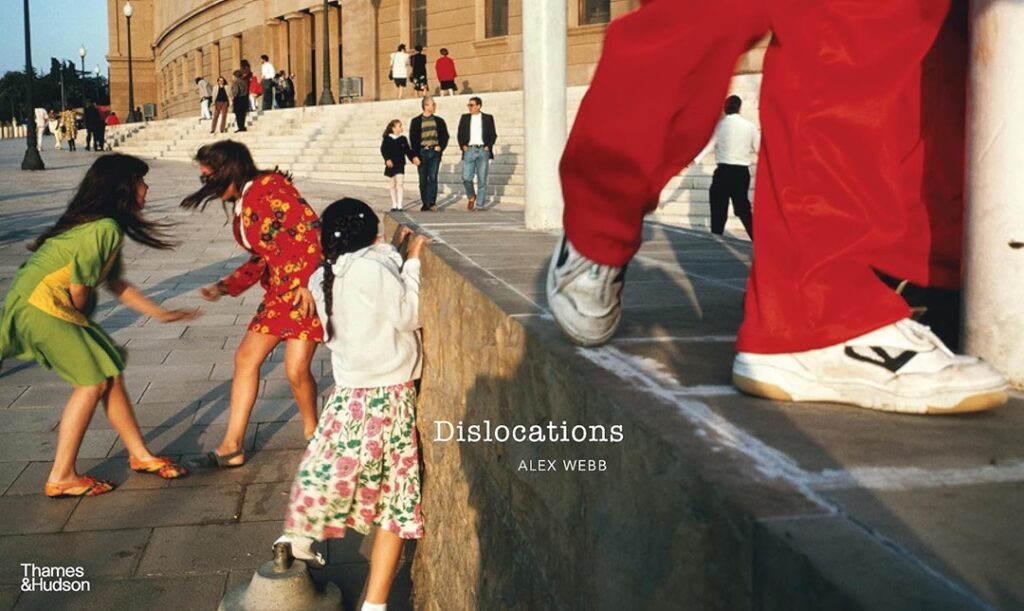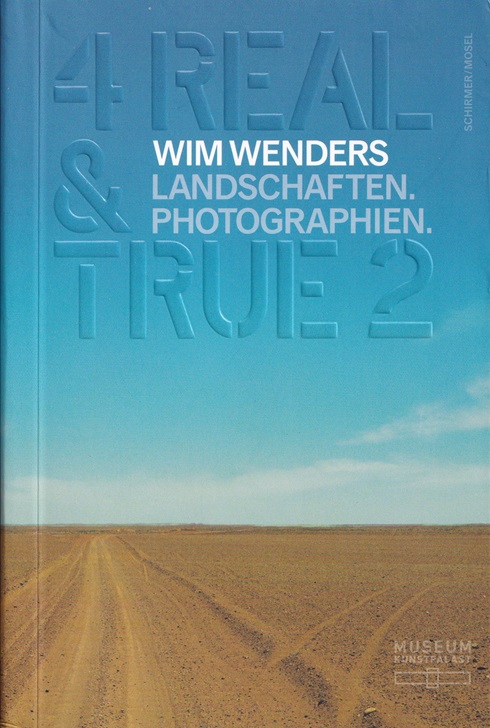私がフォトブックのガイド本「アート写真集ベストセレクション101 2001-2014」(玄光社)を上梓してから早くも約10年が経過した。2014年以降も数多くのフォトブックが刊行されたが、私の知る限りでは、それらを網羅して紹介しているガイド本は存在しないのではないか。この間に情報の発信と受信がコストの低いネットに大きくシフトして、紙媒体の出版業界が非常に厳しい環境に直面するようになる。
ネットでのフォトブック情報はとても手軽で便利だ。しかしメディアの性格上、発信者の主観的な情報が多様にまた局地的に存在することになる。またネットの世界は利用者ごとにパーソナライズされ最適化されたコンテンツが表示されがちで、どうしても自分の興味ある写真家やカテゴリーの本の情報しか見えなくなってしまう。過去約10年に起きたのは、フォトブック情報の多様化という名の無秩序化のカオス化であったともいえるだろう。

その混沌の中、多くの人は自分好みの情報だけに局地的に触れていて、それがすべての世界だと思い込んでいたのではないだろうか。
ではどのように膨大な情報を秩序化するかというと、できるだけ客観的な視点でセレクションされた発売年ごとのフォトブック・ガイドの制作だろう。そのようなブックリストが存在すれば、何を買ったらよいかの目安になると思う。
以上の考えで、あまたあるこのブログにまた新たにカテゴリー「発行年別フォトブック・ガイド」を追加することにした。前著は2001-2014年となっているが、実は2014年刊行の本は1冊しか紹介していない。したがって、これから機会のあるごとに2014年から現在までの年ごとの重要なフォトブックをリスト化して紹介していきたいと思う。
理想は紙の書籍の形式だ。一覧性がありページ数が多い雑誌や本だと色々なフォトブック情報を幅広く紹介できるので、自分の知らない分野のものを知るきっかけになる。だがとりあえずは、将来の書籍化の可能性にかけて、原稿を書き溜めていくつもりで取り組みたい。この出版不況の中、もし興味ある出版社があればぜひお声掛けいただきたい。このブログのもう一つのカテゴリーでもある「ファインアート系ファッション写真のフォトブック・ガイド」も、もちろんライフワークだと思って紹介予定の本を買い進めている。個人的にはこちらの方が幅広い層の人に売れると考えている。
またもしフォトブックのセレクションや編集に協力してくれる人がいれば大歓迎だ。一人なら内容に勘違いや間違いがあるかもしれないし、重要なフォトブックを見落としている可能性もある。多くの人が確かめてくれれば信頼できるフォトブック・ガイドになると思う。
フォトブック・ガイド 2014年版 (1)
・Robert Frank: In America
Robert Frank (ロバート・フランク)
出版社: Steidl (2014/11/30)
SBN-10: 3869307358
ISBN-13: 978-386930735
出版社のウェブサイト

ロバート・フランク(1924 – 2019)の「The Americans」(1959年刊)は、アメリカ人のアイデンティティーの試金石であるとともに、写真史上の名作フォトブックといわれている。しかしその後、彼がすぐに映画制作に転向し、また70年代に全く新しいスタイルで写真界に復帰したことから、同書掲載83点以外の初期作品は忘れ去られていた。
本書はスタンフォード大学のカンター・アート・センター(Cantor Arts Center)で2014年秋に開催された、50年代アメリカで撮影されたフランク作品に初めて注目した展覧会に際して刊行。1991~2011年までニューヨーク近代美術館の写真部門チーフ・キュレーターだったピーター・ガラッシ(Peter Galassi)が企画編集を担当。未発表作による「The Americans」の第2巻ともいえる内容だが、収録131点中の22点はオリジナル版収録作と重複している。ガラッシはエッセーで、フランクのルーツであるプロ・フォトジャーナリズムを探求。また当時主流だったグラフ雑誌と一線を画して、35mmカメラで作家性を確立させた彼の革新的な写真提示方法を分析。1949~1961年にわたる全米旅行の過程を記した見開きの詳細マップ”Locations of photographs in 「The Americans」 and 「Robert Frank in America」”も収録され、収録写真のページ・ナンバーが地図の撮影地横に記載。「The Americans」が好きな人は必読。
ハードカバー: 195ページ、サイズ2.5 x 23.5 x 24.8 cm、モノクロ131点を収録。
(マーケット情報)
状態により、50ドル(7,500円)~100ドル(15,000円)程度で購入可能
・Josef Koudelka: Exiles (英語)
Josef Koudelka (ジョセフ・クーデルカ)
出版社: Thames & Hudson Ltd; 2nd Revised版 (2014/9/22)
SBN-10: 0500544417
ISBN-13: 978-0500544419
出版社のウェブサイト

ジョセフ・クーデルカ(1938-)は、旅に生きるチェコスロバキア出身の写真家。60年代からエンジニアのかたわら劇場写真家としてキャリアを開始する。1961~1967年にかけて主に東欧でジプシーを撮影。1968年には反ソ連デモが続くプラハへのソ連軍侵攻をドキュメント。1970年に英国に亡命し、1971年よりマグナム・フォトのメンバーとなる。
被写体のジプシーのように、自由に放浪する生き方自体をテーマとしたクーデルカの作家性はアート界でも広く認められるようになる。いまでは世界中の美術館で展覧会が開催されるとともに、作品がコレクションされている。2013年に東京国立近代美術館で個展、2014年には米国で回顧展が行われている。
本書は、クーデルカが祖国を脱出後に欧州や米国を放浪しながら撮影した代表作「Exiles」の待望の改定版。「Exiles」は流浪者や亡命者の意味。彼は広告や報道の仕事を行うよりも、自由に放浪する生き方をえらび、世界各地の辺境で生きる運命を受け入れている人々の誕生、結婚、死などの日常生活を粘り強く撮影している。特にスペイン、アイルランド、イタリア、ギリシャなどの同じ場所を何度も訪れている。
本書のオリジナル版は、1988年にパリの国立写真センターとニューヨークのICP(国際写真センター)で行われた展覧会の際に刊行。(フランス語版、英国版、米国版が同時刊行)
新版では未発表作10点が追加収録されている。エッセーは、クーデルカの写真集や美術館展企画を手掛けているロベール・デルピエールが担当。
ハードカバー: 188ページ、 サイズ30.4 x 27.4 x 2.4 cm、約75点の図版を収録。
(マーケット情報)
状態により、50ドル(7,500円)~100ドル(15,000円)程度で購入可能
・The Open Road: Photography & the American Roadtrip
David Campany(デビット・カンパニー著)
出版社: Aperture (2014/10/31)
ISBN-10: 1597112402
ISBN-13: 978-1597112406
出版社のウェブサイト
著者のウェブサイト

アメリカでは、ロード・トリップは長きにわたり文化のシンボル的な存在だった。それは自動車が消費者に広く普及して、道路が国中に張り巡らされて以来、可能性と自由、発見と逃避、自己喪失とともに再発見する行為だった。第2次大戦後には、ロード・トリップが文学、音楽、映画、写真で目立って登場してくる。写真家のスティーブン・ショアは「この国は長い旅によって形づくられている。1940年代以降、ロード・トリップは夢と自由と未来の可能性の感覚を象徴しており、文化の中で重要な役割を果たしている」と書いている。
これまでに、ウォーカー・エバンス、ベレニス・アボット、エドワード・ウェストン、アンリ・カルティエ=ブレッソン、エド・ルシェなど、数多くの写真家たちは作品制作のために米国縦断の旅を敢行している。その中で最も有名な仕事はロバート・フランクがまとめた写真集「The Americans」だろう。それ以後も現在までに、スティーブン・ショア、アレック・ソス、ライアン・マッギンレイなど数百人もの写真家たちが写真によるロード・トリップの伝統を受け継いで活動を行っている。
本書では著者デビット・カンパニーは「アメリカのイメージは、ロード・トリップなしには考えられない」と主張し、写真によるロード・トリップを独立した作品ジャンルと取り上げ、この分野の写真家たちの物語を提示している。内容はロード・カルチャーの歴史を探求する紹介から始まり、アメリカのロード・トリップをポートフォリオ作品とともに深く探求した年代順の18章で構成されている。ロバート・フランク、エド・ルシェ、ゲイリー・ウィノグランド、ジョエル・スタンフェルド、ウィリアム・エグルストン、アレックス・ソス、ライアン・マッギンレイなどによる重要ロード・トリップ作品が含まれる。興味深いのは、欧米ではあまり知名度がない藤原新也の1988年作品「アメリカン・ルーレット」が収録されていること。1991年にかつてのジャパンが再結成したレイン・ツゥリー・クロウという英国バンドのアルバム・カヴァーで藤原の写真が採用され、海外で彼の米国の砂漠の写真が認知されるようになったと紹介されている。
またカンパニーは紹介分で「ロード・トリップが終わった後に何が起きるべきか?それは、現状への復帰か? 革命的な新しい人生の始まりか?将来の見通しのいくつかのマイナーな調整だろうか?明らかに西部にドライブしていくだけでは約束の地(Promised Land )に着くことはできないのだ」とも語っている。本書が伝えたいのはアメリカン・ドリームとその挫折の歴史なのだろう。
ハードカバー: 272ページ、サイズ 30 x 25.6 x 3.8 cm、約150点の図版が収録。
(収録写真家)
Robert Frank, Ed Ruscha, Inge Morath, Garry Winogrand, Joel Meyerowitz, William Eggleston, Lee Friedlander, Jacob Holdt, Stephen Shore, Bernard Plossu, Shinya Fujiwara, Victor Burgin, Joel Sternfeld, Alec Soth, Todd Hido, Ryan McGinley, Justine Kurland, Taiyo Onorato and Nico Krebsなど
(マーケット情報)
状態により、200ドル(30,000円)~300ドル(45,000円)程度で購入可能
(フォトブック・コレクションの購入ガイド)
もし欲しい洋書フォトブックが見つかったら、まず通販大手のアマゾンで在庫を検索してみよう。アマゾンでは、新刊と古書を同時に販売している。本の大体の相場観を掴むのにとても便利だ。ここで紹介しているリストにはISBNを記載しているので、この番号をコピペして在庫を調べることから始めればよい。本によっては、流通在庫があり新品で購入可能な場合もある。特に名作の改訂版は、出版社も多めに印刷する場合が多い。売り切れて絶版になった場合、昨今の急激な円安と送料高騰により、もしAmazon Co.jpに日本の業者が本を売りに出していたら一番安い価格である可能性が高い。しかし、古書の場合は新品と違い状態は個別の本ごとにかなりばらつきがある。また状態の良し悪しの判断は主観的だ。もし状態にこだわるのなら、古書店や専門店に行って個別に状態を確認して納得したうえで購入することを薦める。ブリッツで定期的に行っている「Photo Book Collection」ではすべての本の状態を確認できる。
フォトブックの在庫は海外の専門サイトで豊富に発見できる。まずは、アマゾンの米国、英国などのサイトで在庫を検索してみよう。送付先の住所を日本に登録しておけば、個別の業者の送料も提示される。海外の大手検索サイトを利用すると専門店の在庫も簡単に見つかる。しかし海外から買う場合、いま円安とともに送料がかなり高額になっているので注意が必要だ。特にフォトブックはサイズが大きいうえに重量がある。本自体の値段を超える送料がかかる場合も普通に起きている。最初の見積もりよりも実際の送料が高くて、追加料金を請求される場合もある。もし状態に納得しなくて返品する場合も、送料がかかってしまう。私は興味深いフォトブックが出たら必ず新刊で買い求めるようにしている。
フォトブックを写真が掲載された「本」だと考えると高級品だと感じるだろう。しかし、趣味のファインアート写真コレクションの入門分野だと考えると、見方が変わるのではないか。写真やフォトブックと同様に、いまや他分野のすべてのアート作品やコレクタブルもとても高額になっているのだ。実はフォトブックはいまでも比較的低予算で開始できるコレクション分野なのだ。
(マーケット情報の為替レートは 1ドル/150円換算)