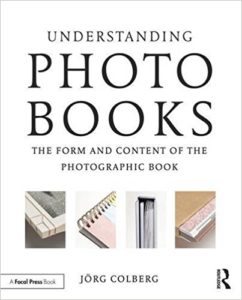アート・フォト・サイトで行っている講座では、よくアート写真の世界で成功する方法を教えてくれと質問される。私は、成功自体を求めないことだ、などと禅問答のようなアドバイスとを返すことが多い。
成功とは何か。たぶん多くの人は、写真作品が世の中で評価され知名度が上がり、個展開催、写真集出版、そしてオリジナルプリントが高額で売れたりするようなイメージを持っているのだろう。しかし、現実的にはそのような成功イメージが短い期間で実現する可能性は極めて低いといえるだろう。最初は自分の能力と可能性を信じて、作品制作に時間と費用をかける。しかし、評価がないどころか無視されるのが当たり前、まして販売に結び付くことなどはない。つまり、成功イメージを持っていると失望してしまい作家活動を辞めてしまう可能性が極めて高い。だから逆説的に短期的成功を求めないことが継続の基本になる。継続する限り成功する可能性がある、というのが上記の禅問答の意味なのだ。
世の中には、成功者のキャリアを分析して、同じように心構えを持って行動すれば成功するというビジネス書が溢れている。上記のような質問をしてくる人は、アート写真における同様の成功哲学を知りたいという意図なのだろう。若い時は、ある程度の能力があり、積極的に努力して頑張ればビジネスの世界で成功すると信じているもの。しかし、年齢を重ねていくと、実は社会での成功の大部分は運により決まるという認識が、長く苦い実体験を通して培われるようになる。先日に亡くなった野村克也氏の座右の銘に、江戸時代の大名松浦清の発言として知られる、「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」がある。人生での成功は運によるとしても、その確率を高めるには、できる限り失敗を避ける準備を怠らないことにあるような意味だと解釈している。それはアート写真の作家活動では何に当てはまるのか?作家活動の成功確率を高めるために、絶対に踏んではいけない地雷、つまり避けなければならないことを考えてみよう。
アートの世界で一流と言われる写真家/アーティストが、私は自分の直感を信じて作品制作を心がけている、というような発言をしているのを聞いたことがあるだろう。しかし、私はあえて若手新人は直感に頼りすぎないことを心がけてほしいとアドバイスしたい。
ややわかり難いかもしれないが、既に評価されている経験豊富な一流アーティストと、経験が浅い人との「直感」の本質は全く違うという意味だ。一流写真家は、いままでに様々な作品制作を行い、膨大な過去の作品に対峙して思考している。また人生経験も豊富で、結果として幅広いスキルを持っている。彼らは、それらを通して世界を見ているともいえる。過去の先人たちの偉大な仕事の流れと、深いところで繋がっているのだ。入ってくる無数の情報は、積み重ねられたフィルターを通り、無意識の深いところで重なり合い、突然変異や新たな組み合わせがおき、結果として直感が生まれてくる。
若手新人は、当然のこととしてスキルがまったくない。かれらに自然浮かんでくる直感はどこから生まれかというと多くの場合、単に思い出しやすい、想像しやすい情報から本能的にもたらせるのだ。この二つの直感の区別は極めて難しい。また直感を信じている人は何かを学ぶ必要性を感じない。趣味のアマチュア写真家なら全く問題がない。しかしアーティストを目指す若手新人は、一流と言われるまで、様々なことを学び経験してスキルを獲得していかなければならない。
直感に頼りすぎると、次第に思い込みに囚われて柔軟な姿勢がなくなる点も指摘しておこう。非常に多くの若手新人が、自分がいったんまとめたポートフォリオに囚われてしまうのだ。そして、ひたすらそれを認めてくれる人を探しにポートフォリオ・レビューを回ったりする。またデジタル印刷普及により写真集制作の敷居が非常に低くなった。写真集というモノが出来上がると、自作への思いはさらに強化されてしまうのだ。
作品は長い時間をかけて、世の中に触れることで常にアップデートを続けなければならない。自分のメッセージが伝わらないと判断したら、作品制作を断念して、新たなテーマを世の中で再び探す勇気も必要なのだ。多くの人を感動させるようなメッセージを持った作品は簡単には制作できない。一般的な人間は、自然と湧いてきた直感とそこから持たされる思い込みに囚われやすいという心理的特徴を持つ。やや抽象的だが、突き詰めるとアーティストは、そのような一般人に新たな視点を作品で提示して、彼らが自らを客観視するきっかけを提供する人なのだ。だから創作する人は、それを意識したうえで常に自らを客観視する姿勢を持たなければならない。自分が違和感を持つことを無視せずに、あえて対峙する勇気を持つのだ。直感を信じ思い込みに囚われてしまうと、若い時点で進歩が完全に停滞してしまう。
そのような、根拠なき自信に満ちあふれた若手新人でも、中には何らかのきっかけで思い込みに気付く人がいる。誰かが、嫌われることを覚悟して、彼らがフレームの中で凝り固まった見方をしている事実を指摘しなければならないと考える。私がいつも繰り返し言っているように、「アーティストとは、社会と能動的に接する一つの生き方」だと気付いてほしい。