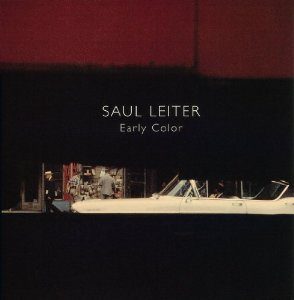
ソール・ライター (1923-2013)は、83歳の時にシュタイデル社から刊行された“SAUL LEITER Early Color”(2006年刊)がきっかけで再評価された米国人写真家。2013年11月に亡くなっているのだが、ここにきて再び注目を集めている。
昨年春に渋谷Bunkamura ザ・ミュージアムにて開催された「ニューヨークが生んだ伝説 写真家ソール・ライター展」は、総入場者数8万3000人を超え、図録の“ソール・ライターのすべて”(2017年、青幻舎刊)は異例のベストセラーになったという。
その写真展が2018年4月から伊丹市美術館に巡回、また今月には彼の女性ヌード作品を紹介する“ソール・ライター写真集 WOMEN”も刊行された。シュタイデル社からも同様のヌード写真を集めた“In My Room”が刊行予定だ。ニューヨークでは限定250部の豪華本“The Ballad of Soames Bantry” (Lumiere Press/Howard Greenberg Gallery刊)が刊行され話題になった。
私どもは日本独自のアート写真の価値基準として限界芸術の写真版のクール・ポップ写真を提唱している。その定義はかなり複雑なのでここでは触れない。興味ある人はぜひ過去のブログで”日本のアート写真の新価値基準”を読んでみてほしい。
実は海外の20世紀写真家のなかに、長年作品制作を続けた結果、複数の人に見立てられて最終的に作家性が認められた、いわゆるクール・ポップ的な人がいたことに注目している。ソール・ライターもその写真家に含まれるのではないかと考えている。
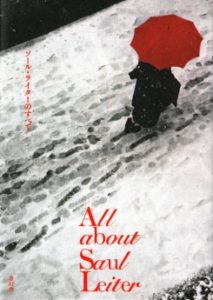
“ソール・ライターのすべて”(2017年、青幻舎刊)の195ページにマックス・コズロフ(美術史家、評論家)のライターへの発言が引用されている。「マックス・コズロフが、ある日私にこう言った。『あなたはいわゆる写真家ではない。写真は撮っているが、自分自身の目的のために撮っているだけで、その目的はほかの写真家たちと同じものではない』彼の言葉が何を意味するかはちゃんと理解できたかどうかは分からないが、彼の言い方は好きだ」また、「仕事の価値を認めて欲しくなかった訳ではないが、私は有名になる欲求に一度も屈したことがない」(211ページ)とも語っている。また別のインタビューでは「無視されることは、大きな特権です」とも語っている。
今回は、彼のファッション写真とヌード写真を通して彼のキャリアを振り返り、彼の作品創作の背景と、どのように彼のアート性が見立てられたのかを探求してみたい。
・ファッション写真でのアート性の追求
私はアートとしてのファッション写真を専門にしている。ファッション写真は、長い間作り物のイメージであることからアート性が低いとされていた。本格的に美術館で展示され、ギャラリーやオークションで取り扱われるようになったのは1990年代になってからだ。それ以前のファッション写真家は2種類に分けられる。仕事と割り切っクライエントが求める服の情報を伝えるヴィジュアルを制作し続けた人。そして、ファッション写真の延長線上にアート性追及の可能性があると信じて、数ある制約の中で独自の表現に挑戦した人だ。いま市場でアート性が再評価されているのは後者の人たちだ。
しかし実際のファッション写真の現場は、クライエントやエディターからの強い要求があり、写真家の自由裁量の余地はあまり大きくなかった。その状況でできる限り自分の創造性を発揮しようとしてきたのが、ギイ・ブルダン、ブライアン・ダフィー、ポール・ヒメル、ルイス・ファーなどだ。
ソウル・ライターもその中に入ると考えている。以前も紹介したが、彼はファッション写真について「私が行った仕事を否定する気はないが、ファッション写真家としてだけ記憶されるのは本意ではない」と語っている。また「仕事で撮影した写真が結果的にファッション写真というよりも、それ以上の何かを表現する写真に見えることを望んでいる」と語っている。
彼は1958年の高級ファッション誌“ハーパース・バザー”の仕事をかわきりに、80年代まで、“ELLE”、“Queen”、“ヴォーグ英国版”、“Nova”、“Snow”などでも仕事を行っている。彼のキャリアの特徴は、写真家として活躍していた時期も常に画家として創作を継続してきたこと。画家を目指していて、結局写真家になる例は多いが、ライターは写真と絵画の両分野で表現を行っていたのだ。彼のファッションやストリートの写真の特徴の、大胆な構図、叙情的・絵画的な色遣いなは、画家の視点があったからこそ表現できたのだ。
キュレーターのジェーン・リビングストンは、“The New York School”(1992年刊)で、ライターのカラー作品は、いままでの他のファッション写真と比べても唯一無二だ、と指摘している。
しかし、彼は1981年に商業用スタジオを閉鎖してしまう。年齢的にはちょうど60歳手前なので引退を考えた可能性はある。もしかしたら、彼のあこがれるアンリ・カルチェ=ブレッソンのように、キャリア後期は絵画制作に費やそうと考えたのかもしれない。しかし当時の状況を鑑みるに、たぶん彼もファッション写真でのアート性追求に限界を感じた面もあったのだろう。実際のところ、90年以前に活躍した多くのファッション写真家はその将来の可能性に失望して、業界を去るか、他分野の創作に取り組むようになる。ここからは私の一方的な想像なのだが、ライターは他の多くの写真家のように絶望したり自暴自棄に陥ることはなかったのではないか。絶望は未来の希望がかなわないという精神状態だ。ライターの関係資料には、彼が禅的な思想をもって生きていたと書かれている。それは、彼は未来のために現在を生きるのではなく、今という時間に生きようと考えたことを意味する。キリスト教などは未来に生きる宗教だ。時間は過去、現在、未来と継続していて、将来に天国に行くことを目指して現在を生きる面がある。多分、ライターはそのような考え方に違和感を感じて、親の希望した宗教指導者の道に反して画家を目指したのだろう。彼は親の意思に反して生きることを決めた時期から、未来のためではなく、今という時間を集中して生きようと考えたと推測できる。彼はファッション写真のアート性追求に限界を感じても腐ることなく、また未来に期待することなく、今という時間に写真以外のアート表現を続けたのだ。また作品制作は精神を安定させる一種の瞑想のような行為だったのかもしれない。
(2)につづく




